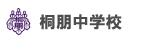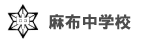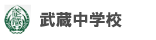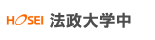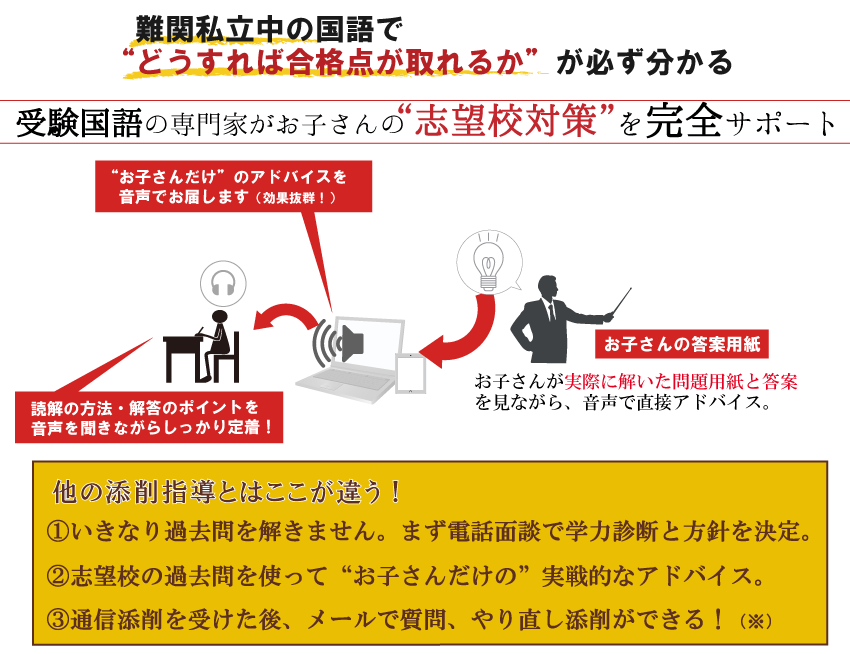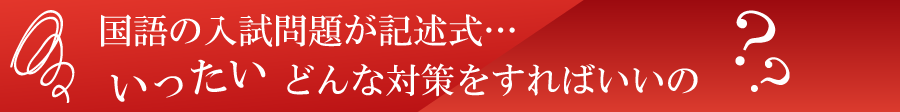
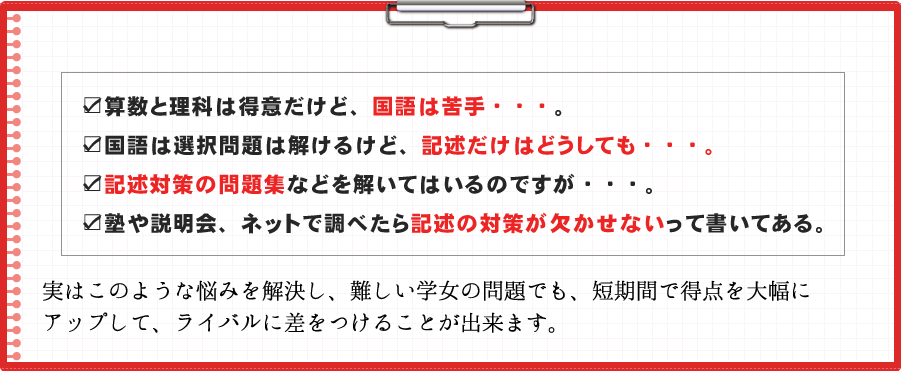

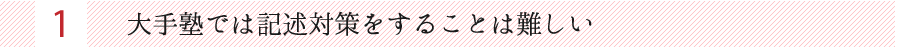
���m���͂��߂Ƃ��A�ǂ�ȂɗD�ꂽ�m�ł��A�Y��w�����ł��Ȃ�����������܂��B
- �����̊w�Z�̖��X���ɍ��킹�u�lj��v�u�I�������v�����Ƃ̒��S�ɂȂ�
- ���w�̓Y��͓Ɠ��̓��������A�����܂ł̌o��������搶�����Ȃ�
- �Y��w���͂P�x�����łȂ��A�Q�A�R��s�����ƂŌ��ʂ��o��B���̂��߁A���m�̐搶�� �P�l�P�l�ɂ����܂Ŏ��Ԃ��������Ƃ��ł��Ȃ�

���\���Z�͍̉��m�����ɋ����[�����͌��ʂ����J���Ă��܂��B
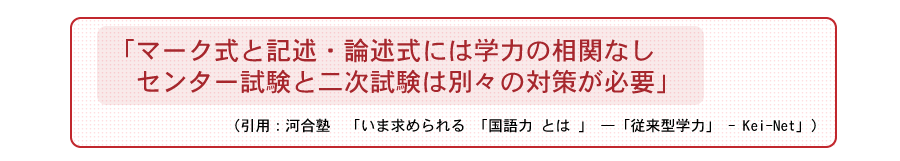
���̃��|�[�g�́A�͍��m�������̖͎��Ɓu�S���w�́E�w�K�����v�͂������ʂɏo�����̂ł���A �����̌���̐搶���F�����Ă��邱�Ƃ��Ǝv���܂��B
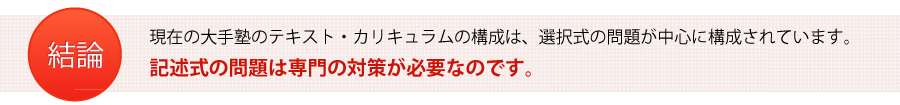
�}���J���A�����Ȃǂ̍œ�֒��w�Z�̓����ł́A�q�����g�����S�������̕��͂������Ƃ��� �h�L�q���S�h�̉����߂��Ă��܂��B�I�m�Ȓ���_�������A�����Ɏ���u�l�����v�ĂɁh�L�q�h���Ȃ�����i�ł��܂���I���̋L�q�͂�g�ɒ�����ɂ́A�W�c�m�́u���K���S���Ɓv�ł͍���ł��B�W�c�m�ł́u��̐�����A����v���邾���̎��ƂȂ̂ŁA�Ȃ��Ȃ��L�q�͂͌���Ȃ��̂ł��B

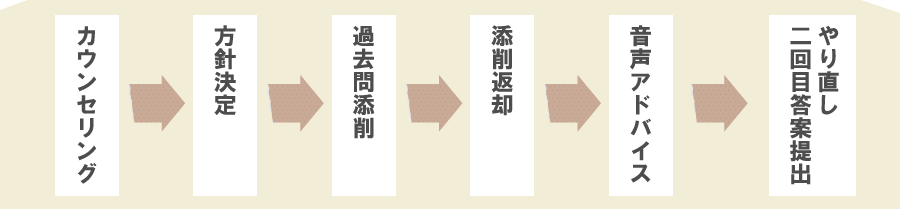

�P�l�P�l�̊w�K���B�x����E���ӕ���̏Ȃǂ��l�����āA�ǂ̔N�x�̉ߋ���ɒ��킷�邩���ʂɎw�����܂��B�ꍇ�ɂ���Ă͓����^�C�v�̖�肪�o���ꂽ���̊w�Z�̉ߋ���������w�������邱�Ƃ�����܂��B��O�Ƃ����łȂ��A�������̎Z�̉ߋ�������͂��Ă��܂��̂ŁA���ʂȂ������I�Ȏw���ɂ��u�]�Z�̌X���ɉ��������̉�������l�������g�ɕt���܂��B

�����̉̍̓_�����Ȃ��Ȃ��Ƃ����Ȃ����w�K�m�̍̓_�����ƈႢ�A���ۂɑ��m�̖͎��̍��o���̂���v���u�t�������A���̈Ӑ}�����ݎ�������ł��Ă��邩�ǂ������������茩�č̓_���܂��B


���̂悤�ɁA�S�ʂ��^���ԂɂȂ�قǂ̓Y�킪�Ȃ���Ă��܂����A���ہA���ʂɂ͏�������Ȃ��قǎw��������e�͑���ɂ킽��܂��B �܂��A�ʎw���ɒʂ��Ă��鐶�k�̏ꍇ�́A�Y��͂��ꂼ��̐��k�̓����̎w���ɂ����Č��O����Ă���|�C���g�i���ӗ͂��Ȃ�������A���Ⴂ���₷���Ȃǁj���������čs���A���ڕ⑫��t�������Ȃ���w�����s���܂��B

�ߋ�������������k�̉́A���k���ꂼ��ɂ���ĈႢ�܂��B�͔͉ƌ���ׂĂ݂āA�ǂ����ǂ������悢�̂��H���k�������ł݂āi�������͐e��l���݂Ă����l�ł��j�A�����ɂ킩��ł��傤���H����͔��ɓ�����Ƃł��B
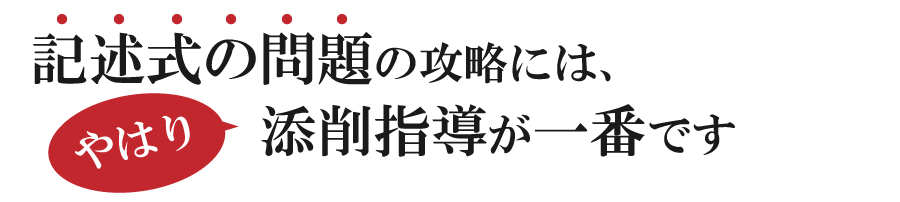

�L�q���̑�Ɂu���W�v�����������ł͌��ʂ�����܂���B �Ȃ��Ȃ�A�����ǂ����ł͋L�q�͂͏オ��Ȃ�����ł��B �m���Ɂu�����|�C���g�v�͂킩��܂��B�������A���������Ă݂�� �u�����ł͂ł�������v�ł��A�v���̍̓_�҂��炷��ƁA�܂������I�O��ȉɂȂ��Ă��邱�Ƃ��悭����܂��B
���̓_�Ɋւ��āA��w�̏��_���œ��{��̓Y��w�����т������� �T��搶���A�Y��w���Ɋւ��Ď��̂悤�ɂ��b���Ă��܂��B
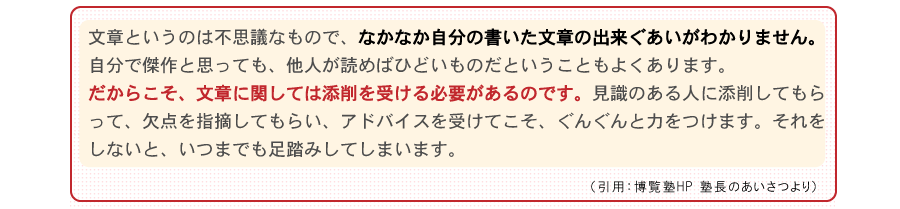
���ɏ��w���̏ꍇ�́A�͔͉�ǂނ����ŋL�q�����Ȃ�Ƃ������Ƃ͂���܂���B
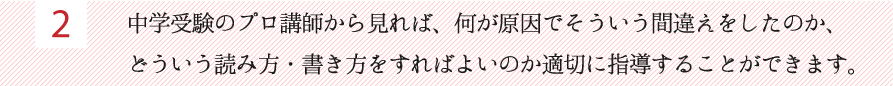
�����炱���A�L�q�Ɋւ��Ă̓v���̓Y�����K�v������̂ł��B

�u�Y�킪�K�v�Ȃ��Ƃ͕�����܂����B���ǁA���̓Y��͒N�ɗ��߂�����ł����H�v�Ƃ��l����������܂���B
�Y������Ă����搶���̂����Ȃ��A�Y�킵�Ă��ꂽ�Ƃ��Ă��A �뎚�E�E���������A�͔͉Ɣ�ׂĈꕔ������Y�킷�邾���A�Y�킵�Ă�����Ă� ���ǂǂ�����������������Ȃ��B�Ƃ������Ƃ��{���ɑ����ł��B
�Y��͂��q����̊w�͂ɍ��킹�āA�lj��̕��@���獪�{�I�Ɏw������K�v������܂��B
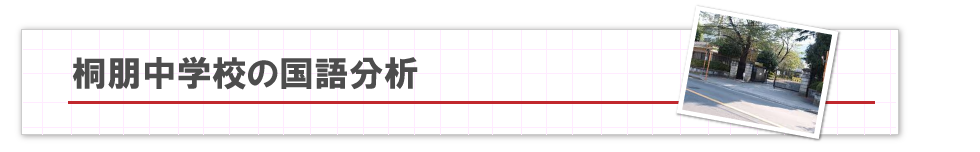
�Z�`��
100�_���_/50�� ���2~3��i�lj���~�Q�{�N�x�ɂ���Ă͊����̏�����肪����ɓƗ���j
�Z�X��
�E�����E���ꕶ����1��A���M�I�ȕ��͂�1��B�_���E�������͏o�肳��Ă��Ȃ��B
�E���2��\������{�B20�N�x�̂悤�ɁA�Ɨ����������̑�₪�o�肳�ꂽ���Ƃ��B21�N�x�ȍ~�́A�lj���̒��ŁA�����⊵�p���₤�B23�N�x�ł́A�u�����܂��v�u�����ÁX�v�u�d���Ήv�u�����v�u�h���v�Ȃǂ����ꂽ�B
�E�ݖ�̓��e�́A�L�q��肪�����B��N�A�����������Ȃ��A�u�킩��₷���������Ȃ����v�ƌ�����肪5��O��B�����o�����v�f�ō\���ł�����̂ł͂Ȃ��̂ŁA�u�����̌��t�Ŗ{�@���̓��e����Ղ��`����́v���K�v�B
�E�w�K�@���q�̍���́A�قƂ�ǂ̖�肪�L�q���B�������A����������1�s���x�̋L�q�ł͂Ȃ��A�����������Ȃ���A�{���̓��e�������̌��t�Ő�������Ƃ����{�i�I�ȋL�q��肪�唼�B
�E�L�q�̓����Ƃ��āA���̒��ɍ�⑤�̉��߂������Ă���_�B�Ⴆ�Ε����Q�O�N�x�̑��Q��̖�V�Łu�T�����Ƃ��邪�A�M�҂͎����Ɗ۔�����̎d���̂�����ɑ傫�ȍ������邱�Ƃ�Ɋ����Ă���悤���B�ł́A�ǂ̂悤�ɈႤ�ƍl���Ă��邩�v�ƁA��蒆�̉��߂�O��Ƃ���`�ɂȂ��Ă��܂��B���̉��߂܂����Ɏ����̉��߂ŗՂ�ł��܂��ƁA�����ƂȂ铚�Ă͍��Ȃ��̂Œ��ӂ��K�v�B
�E�L���I������\�ʓI�ȉ��߂ŗՂނƊԈ�����I������I��ł��܂��댯���������B�����Q�O�N�x���P��̍ŏI���́A�ꌩ���ĒZ�����̑I���������ԁB�o��l���̐S���₤���̂����A�T�����O�̕��̗͂U���Ɉ�������ꂸ�ɁA���͑S�̂̐l���Ԃ̐S��̂��Ƃ肩��o��l���̋C�����̓�����[���ǂݎ�邱�ƁB
�E����ȃe�[�}�ł͂Ȃ����̂́A50���̎������ԁA6000���ȏ�̕��͗ʁA5����x�o����鎚�������̂Ȃ��L�q�Ȃǂ��l����ƁA���l�̂��ɁA���x���̍��������B
�E�j�q�Z�ł͂��邪�A23�N�x�ɏo���ꂽ�w�g�C���̐_�l�x�i�A���ԍj�̂悤�ɁA�������_�̕��͂����グ���邱�Ƃ��B
�E��蓯�m���֘A�������ĂP�̃X�g�[���[���`�����Ă���̂ŁA���̖����Q�l�ɂ��Ȃ�������i�߂�悤�ɁB
�E�����̏������͍Œ�ł�7��A�����Ƃ���15��B
�Z��
�E�o��l���̐S���u�s�ԁv���ׂ����₤��肪���������ȓlj�͂��K�v�B�ǂ݂₷�����͂����łȂ��A�l�X�ȃW�������̕��͂ɐG���B
�E�u��������₷���������Ȃ����v�Ƃ����悤�ȁA�u�����̌��t�v�Ő�����������ɂ́A�v�_���܂Ƃ߂邾���łȂ��A��蕶�̓��e�������Ȃ�ɐ������ĕ��͂ɂ���u�\���́v���K�v�B
�E�L�q���ɂ͎��������͂Ȃ����A�L�q���ŗL���ȕ������w�Z�Ƃ͈قȂ�A����2�`3�s���x�̂��̂������̂ŁA�K���Ȓ����ɉ��܂Ƃ߂�K�v������B�K�v�ȃ|�C���g�ɍi���ėv�f�荞�݁A���������ł���悤�ɁB
�E����������́A�o�萔����l����ƁA�z�_��1���ȏ���߂�B������Ȃ��悤�ȓ���Ȗ��͏o����Ȃ��̂ŁA�m���ɓ��_�ł���悤�ɁB
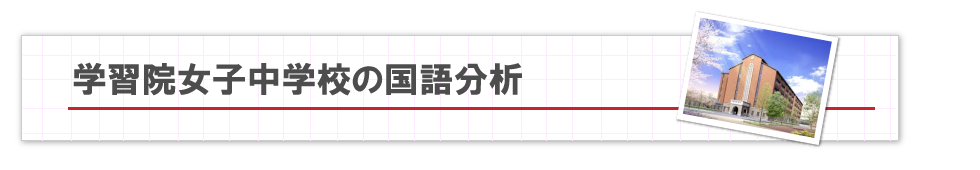
�Z�`��
100�_���_/50�� ���2�`3��i�lj��肪1�`2��ƁA�����̏������1��j �L�q70�� ���i�Œ�C��62��
�Z�X��
�E�����E���ꕶ����1��A���M�I�ȕ��͂�1��B�_���E�������͏o�肳��Ă��Ȃ��B
�E�N�x�ɂ���Ă͘_���I�ȐF�ʂ��@�������̂�A���|�F���Z�����̂��o�肳���B
�E��N�A�lj��̈��p���������B
�E�ݖ␔�́A�lj����12����x�A������20����x�B�lj��肪1��ł�2��ł��A���͗ʂ�6000�����x�ŕς��Ȃ��B
�E�w�K�@���q�̍���́A�قƂ�ǂ̖�肪�L�q���B�������A����������1�s���x�̋L�q�ł͂Ȃ��A�����������Ȃ���A�{���̓��e�������̌��t�Ő�������Ƃ����{�i�I�ȋL�q��肪�唼�B
�E�ו��̓ǂݎ��A�S��E��i�̓ǂݎ��A��g�\���̈Ӗ��A����S�̂̍\�������邱�Ƃ������B
�E�����̓ǂ݁E�����́A��Փx�͍����Ȃ����̖̂�萔��20��قǁB
�E�w�K�@���q���̋L�q�ʂ͓�֒j�q�Z���ł���B�����܂ł̋L�q�ʂ����߂�w�Z�͏��q�Z�ł͒������B
�Z��
�E��l���̋C�������ω������w�i�E���R�E���������Ƃ������A�u�L�q���ʼnɐ��荞�ނׂ��|�C���g�v����������B
�E���ɉ����R�s�ɂ��y�Ԃ̂ŁA�|�C���g���܂Ƃ߂邾���ł̓X�y�[�X���]��B�����̌��t�œ��Â������Ă�����Ƃ��K�v�B�����A���̂Ƃ��A�u�����Ȃ炱���v���v�Ƃ�������ϓI�ȉ͓_���Ɍ��т��ɂ����̂ŁA�v���ӁB��l����������̏��N�����Ƃ�������ړ����₷�����͂��o����邱�Ƃ������Ȃ��Ă��܂����A��蕶�̃|�C���g���q�ϓI�ɓǂݎ���ē�������͂��K�v�B
�E�����̏o�萔�������̂ŁA���W�Ȃǂ��g���Ē��J�Ȋw�K���K�v�B
�E���S���w�����Ɖ��F�w���ƌX�������Ă���
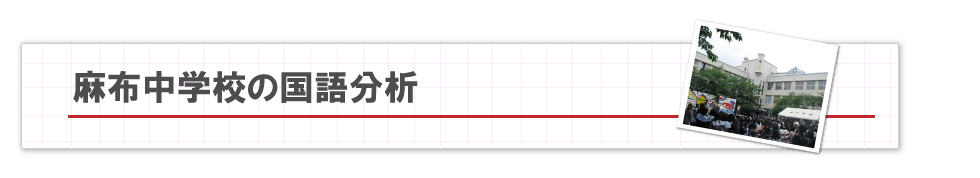
�Z�`��
60�_���_/60�� ���P�� �L�q�@85�� �Œፇ�i���C���@55��
�Z�X��
�E��{�I�ɕ��ꕶ�ł���B���w�����ł́A�_�����␏�M�����嗬�ɂȂ����X�������钆�ŁA���ꕶ���ނƂ��đI�ё�����p���ɁA���z���̓������ւ̃|���V�[��������B�������A���̑�ނ̂قƂ�ǂ������A���R�A�����T���ȂǓN�w�I�e�[�}�������Ă���B�܂��A���������̕��͂��D�܂�A�ƒ����l���W�����G�Ȃ��̂���ނƂ��Ă悭�o�肳���B���M����2��o�肳�ꂽ�N�����������A��{�I�ɂ͕��ꕶ���B
�E�����͕��ς���6000���㔼����7000���㔼�ƁA���Ȃ�̒����ł���B
�E���͑���\���ŁA�����̏�������肪�K���o�肳���B
�E�ݖ␔��12����14����x�ŁA80�p�[�Z���g�ȏオ�L�q���ł���B�i�I�������Ȃǂ͌����X���ɂ���B�j
�E�L�q�̎����͂قƂ�ǂ�30���`60�����x�A�Ō�Ɏ���₤�P�O�O�������^�̋L�q��肪����B30���`60�����x���̐ݖ���e�́A�قƂ�ǂ��S���₤���̂����A��g�\���̈Ӗ���A��i�`�ʂ̈Ӗ���₤���̂�����A��i�̒��ŏے��I�Ȃ��́����i�⓮�A�������グ�A���ꂪ�Î����Ă�����̂�₤�����o�肷��X��������B
�E�u�Ȃ���v���ӎ������ݖ�\���ɂȂ��Ă���̂ŁA30�`60���̋L�q�̐��������A��^�L�q�̐����̃J�M�������Ă��邵�A�ɑ��鎚�����^�C�g�Ȃ̂ŁA�]�v�Ȑ������ł��Ȃ��B
�E�u���_�N��̍����v���v��������ނ�ݖ�B�Ⴆ�A����23�N�x�̏o�T��i�w�����钩�̐�i���Ђ������j�x�́A�ǎ��@�ŕ�炷�Z��ɂ��ẴX�g�[���[�ł����A��6�̐ݖ�Ȃǂł́A�u�Ђ������v��m��Ȃ�����̏��w�����A�u���������䖝�����̋C�����v��z���ł��邩�Ƃ����ƁA�Ȃ��Ȃ�����B���z�̍���́A�ƂĂ�12�̐��_�N��ł͗����ł��Ȃ��S��ω��̋@�q�Ȃǂ𗝉����邱�ƁA�z�����邱�Ƃ����߂��鎎�����e�B
�E���z���͒��w���Ǝ��ɘ_������������قǁA�O��I�ɏ�������w�Z�B
�Z��
�E�����������璷���Ɋ���Ă������ƁB
�E�lj����x���͉��p�ȏ�̂��̂��]�܂�邽�ߐV�����Փx�̍��������ɁA�ߋ���肩��̊w�K���L���B�e�[�}����l�̎��_����̓lj������߂���̂��������߂ɓ�Փx�̍����e�L�X�g���ʍZ����̘_������A���M����I�ю��ۂɉ����B
�E��蕶���ɓǂݖ₢�̎�|�����݁A���̌�A���͂ւ̓lj��ɓ���B���̎��_�Ŗ�肪��������͉̂����܂����A�{�Z�ł͏����ǂ����ł͉ł��Ȃ���肪�����B�悭�_�|��}�����ǂݍ��݂��K�v�B��@���m���ɗ}����悤�ɁB�Ӗ����|���m���ɗ}�������J�ȓlj�̗͂{�����K�v�B
�E��l�̏펯�i���_�j�⓹���ςƂ��������̂��w��ł������Ƃ��|�C���g�B12�̏��w���ɂ͗������Â炢���̂ł��A��l���猩�����قǓ���Ȃ��悤�Ɏv������̂�����B�����̕��͂�ǂ�ŁA���������ł͌o���ł��Ȃ��悤�Ȑl�ԊW�␢�E�ς�m�邱�Ƃ��K�v
�E�Î��̈Ӗ���₤��肪�o�肳���̂ŁA�ߋ��ⓙ�ł��̖�肪�o�Ă����N�x�̖��������Ƃ��́A�Î����Ă�����̂Ƃ��ꂪ�o�Ă����Ƃ��̎�l���̏�S��̋��ʓ_���l���Ȃ���ǂށB
�E�S��\���Ɋւ���ꂢ��L���ɂ��Ă����K�v������B�Ⴆ�A�Ȃ��E�������E�������܂�Ȃ��E���Ȃ����E����������E�Ȃ���肾�E���߂����E���͊��𖡂키�E�킾���܂肪����A�Ȃǂ��c�����s�Ɏg����悤�ɌP�����邱�ƁB
�E���z�̋L�q�́A���͂̒��ɋL�q�̃q���g������Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�u���̏�ʂ�ɂ����ẮA���������S��ɂȂ邾�낤�v�Ƃ����z������͂��K�v�B
�E�����̏������͕K���o�肳���̂ŁA���m�̊�������m�����A�s�̖̂��W�ȂǂőΉ��B
�E���M���A�������A�C�钆�A�}�g��w������ꒆ�A�a�J����w���a�J�A�U�ʎВ��ƌX�������Ă���B
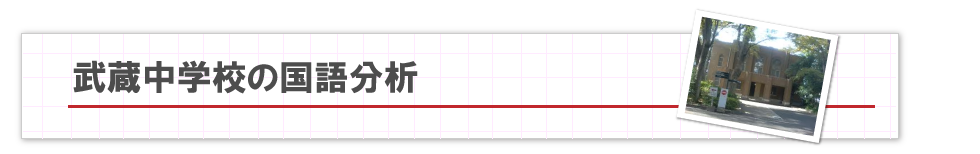
�Z�`��
100�_���_/50�� ���P�� �L�q�@90�� �Œፇ�i���C���@55��
�Z�X��
�E���������̂Ȃ��L�q���v��5��Ƃ����\������{�B�L�q�̉��́A����g���Ȃ��A�]���Ɏ��R�ɋL������Ɠ��̌`���B�����̏��������K���o��B
�E�����̍���́A������O�Ƃ̖��z���l�A�u���ꕶ�v��ӓ|�̏o�肪�����������A�����ŋ߂͐��M�E�_�����n�̕��͂ɃV�t�g���Ă���B
�E�o���i�̌X���Ɋւ��ẮA���ꕶ�̏ꍇ�́A���Ɠ��N��̏��N�E��������l���ɂ�����i�������B�܂��A����23�N�x�̏o�T�w�킪�y�͌��̂��Ƃ����̂ł���i1978�N�o�Łj�x�̂悤�ɁA10�N�ȏ�O�ɏo�ł��ꂽ��i���o�肳��邱�Ƃ��������Ȃ��B�����ŋ߂̏o�T�́A�_���I���͂ł����A�W�������Ƃ��Ă͐��M�Ƃ�����悤�ȍ�i����舵���Ă���B
�Z��
�E������ǂ݉����������x���̍���͂Ƒ��ǔ\�͂��K�v�B
�E�Ƃɂ����O��I�ɋL�q��B��N�A�u�{��������d�v�ƂȂ�L�[���[�h���E���A�����_���I�ɂ܂Ƃߏグ��́v������Ώ\���_���������肪�o�肳��Ă��邽�߁A�u�v��́v��g�ɕt���邱�Ƃ��K�v�B��{���j�Ƃ��ẮA���͂������I�m�ɏE���A���ҁi�̓_�ҁj�ɐ��m�ɓ`������K������B
�E�������N�̌X�����݂Ă���ƁA�u�v��v�̈�����L�q��肪�o�肳��邱�Ƃ�����B�P�ɗv�������ł͐������s�\���ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�������炳��ɘ_���W�J�ł���悤��
�E�u�o��l���̐S����A�s�Ԃ��炭�ݎ��v�Ƃ����L�q��肪����B2008�N�x�i�o�T��i�w�X�q�̉^���i���]�˒q���j�x�j�̖�6�E��7�ł́A�o��l���́u�X�q�ɑ���v���v��₤��肪�łĂ���B��6�́u�F�B���]�Z���Ă��܂����ۂɁA�X�q��厖�ɕ����Ď����A��A�����̕����̉�������ɂ��܂����v�V�[���̋C�������L�q������A��7�́A�u�����Ɉ����Ă����X�q���A��ɐS�̉��ɔ�߂�悤�ɁA��������̉��ɂ��܂����u�S��ω��v��ǂݎ����B�o��l���̊W�������ނ��ƁA�S��̈ڂ�ς��ɃA���e�i�邱�ƁA�S���\�������b�⌾�t�𒍈Ӑ[���E�����ƂȂǂ��|�C���g�B
�E��ɇ@���A���R�B��́̒��ہA��3���ӎ����āA�L�q������K������K�v�B
�E�����W���������킸�A���܂��܂ȕ���ɂӂ���G��A�l���̌����ɂ��āA���̔w�i��Ӗ��������̌��t�ŕ��͂ɂ�����K�B
�E�u����S�����߂悤�Ƃ���v�u�Ƃɂ��������������Ƃ���v�K�v�͂Ȃ��B���ꂽ���ƂɓI�m�ɉł��Ă���A�����ɊW�Ȃ������͂����i����͕����̓����S���̐搶�������j�B
�E�I����́A�S�̖̂�蕶��c�����Ȃ��Ɖ��o���Ȃ����x���̏o��A�����������Ƃ�I�m�ɋL�q����͂�v����قǂ́A�������o�肳��Ă��邽�߁A����[�������œǂ݉����͂�{���B
�E���F�w���A���q���w�@�A�Ó씒�S���w���A�����A���z�A�J���A���M�ƌX�������Ă���B
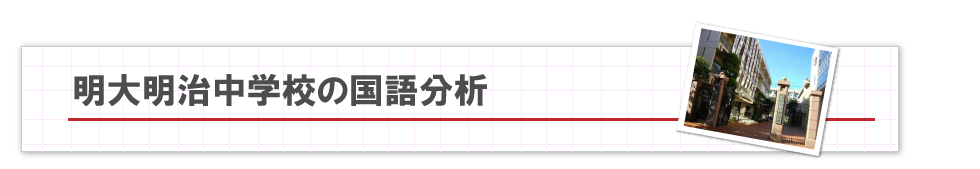
�Z�`��
100�_���_/50�� ���R��i�lj�1�`2��A�����E���Ƃ̒m�����1�`2��j �L�q�@40�� ���i�Œ�C���@60��
�Z�X��
�E21�N�x�ȍ~�A�lj��肪1��A���Ƃ̒m����肪1��A������1��Ƃ����o��\���B20�N�x�ɂ́A���Ƃ̒m�����̑���ɓlj��肪�v2��o���ꂽ���Ƃ��B�m���⊿���̖���30�_�����߂�B
�E�lj���̃W�������́A19�N�x�ȍ~�A�_���E�������̂݁B
�E���͗ʂ�7000�`8000�����x�ƒ��߁B22�N�x�ɂ�5000�����x���������A23�N�x�ɂ�8000�����x�Ƒ啝�ɑ������B
�E�`��������ƁA�I����A����������肪�o����܂����A�L�q���̐��������B���L�q�����Ȃ��Ȃ���25�N�x�ł��A�v5��̋L�q���B�����̌��t�ŗv�|����E�����Ȃǂ���������̂�����A�\���͂��d������Ă���B
�E���N�A�lj���̍Ō�ɁA�u�w�肳�ꂽ�����g����50���ŗv�|���܂Ƃ߂���v���o�����B
�E���Ƃ̒m�����ɂ��ẮA���p��E���Ƃ킴����[�Ԍ��n��̂Ȃ��̊����̈Ӗ���₤���܂ŁA�l�X�Ȗ�肪�o����A������ނ̖�肪�����ďo�肳��邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��B
�Z��
�E�lj���̐ݖ�ł́A�u�����Ƃ͋�̓I�ɂǂ̂悤�Ȃ��Ƃł����v�u�����͉����w���Ă��܂����v�Ƃ����悤�ȓ��ӕ\����T����肪�����A�u�ݖ�ɑΉ�������͒�����f����������́v���A�U���̃J�M�ɂȂ�B���͗ʂ��������߁A�Y���ӏ���T���ĉ�������͂�ǂ�ł���ƁA���Ԃ�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�{����ǂ݂Ȃ���A�d�v�Ǝv����|�C���g�ɐ��������A�u�Ӗ��i���v���A�Ӗ��i�����u�v��v���A������u�ڑ����v�łȂ��A�u�����v��͂ނƂ������ɁA���͂����Ȃ���A��ӂ�ǂޓlj���K���B
�E�뎚�E���E��Ǔ_�E���������i����������8�����x�j���ӎ����Ċw�K�B
�E���ԊǗ����K�v�B���l�̊��ɖ���Փx�������Ȃ������Ǒ����̗͂����߂���̂ŁA��Ɏ��Ԃ��߂��w�K�v����쐬���A�X�s�[�f�B�[�ɓlj��E������K�����B
�E�lj���̍Ō�ɏo�����A�u�w�肳�ꂽ�����g����50���ŗv�|���܂Ƃ߂���v�̂��߁A�u�����ׂ��|�C���g���i��́v�Ɓu���������Ȃǂ��g���āA�������ɂ����߂�e�N�j�b�N�v��{���Ă������Ƃ��K�v�B�ߋ���Ȃǂʼn��K��ς�ł����B
�E�㔼�̂��Ƃ̒m���A�����̏����������m���Ɏ�邱�Ƃ��K�{�B��������A��{���x���̖�肪�قƂ�ǂȂ̂ŁA���W�ȂǂŊ�b�ł߂��������肷��B�����������ꂽ��A�����̏������Ńo�����X�̗���◐�G�������_�ɂȂ������肷�邱�Ƃ�����̂ŁA���J�ɏ������K�A���ɂ����Ă͓�������Ӗ����ׂ������Ȃ��K�����B
�E�w�K�@�����ȁA�w�K�@���q�����ȁA�������w�ƌX�������Ă���B
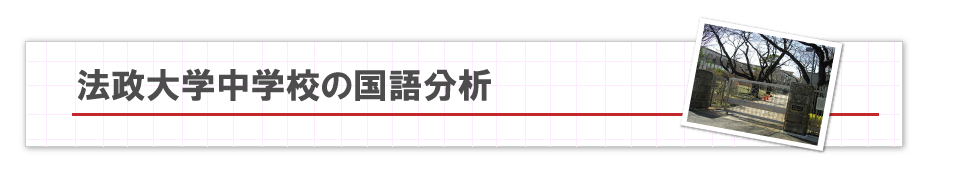
�Z�`��
150�_���_/50�� ���2��A���ݖ␔20�`25����x
�Z�X��
�E4000�`5000�����x�̕��͂�2��o����A�lj�ʂ���⑽����A�L�q�����o�肳��邽�߁A���Ԃɂ��܂�]�T�͂Ȃ��B
�E�lj���̃W�������͑��1���u�����E���ꕶ�v�A���2���u�_���E�������v�Ŕ�r�I�ǂ݂₷�����́B
�E�u�L���I����v���唼�ŁA�u���������v��30�`60�����x�́u�L�q���v���o�肳���B�ݖ�̓��e�́A�o��l���̐S�����M�҂̎����܂Ƃ߂�������́A�����̓ǂݏ����A�ڑ����E�K��E�K���̕�[�A�i���̎��ʁA���p�\���B
�E�ڑ����╶�@�Ɋւ����肪�o����邱�Ƃ��B24�N�x�̑��1�A��3�̂悤�ɁA�u�Úg�v�u���g�v�u��v�u�|�u�v�Ȃǂ̕\���Z�@��₤����A23�N�x�̑��2�̖�7�̂悤�ɁA�u�i���v�ɂ��ē����������肪�悭������B
�E���1�A���2�A���ꂼ��̍Ō�̏��₪�����̓ǂ݁E���������ɂȂ��Ă���
�Z��
�E�S�̓I�ɍ����_�����ɂȂ肪���Ȗ@���̓����ł��A���ɕ��ϓ_�������̂�����B����ŗ��Ƃ��Ă��܂��ƁA����̎��ƍ������Ă��܂��̂ŁA�m���ɓ��_���邱�Ƃ��K�v�B
�E�@���̋L�q���́A30�`40�����x�ƒZ�߂̖�肪�������߁A�����������ɉ��܂Ƃ߂邱�Ƃ��|�C���g�B�u�����̌��t�����̂܂g�킸�A�����̌��t�Ō���������́v�����߂���B���i����A��b�𑝂₷�H�v��������A�Z�߂̕��͂��������K�������肵�Ă������Ƃ���B
�E�u�����ŏ�����Ƃ���������ŏ����Ă��邩�v�Ƃ����Ƃ���������Ă���B���ɁA����ŏo�����Z�߂̋L�q���ł́A�����ŏ������Ƃ��A���������炷���Ƃɂ��Ȃ���B�����̗��K�͖������������A�o���邩���芿�����g���ĕ��������K����g�ɂ��Ă����B
�E�ڑ����╶�@�Ɋւ�����͓�x���������͏o�肳��Ȃ��̂ŁA���W�ł��������b���ł߂āA�ߋ���ʼn��K��ςށB
�E���̍Ō�̊����̓ǂ݁E���������͊�{���x���̂��̂��قƂ�ǁB�������ł͊m���ɓ_���Ƃ��悤�ɁB